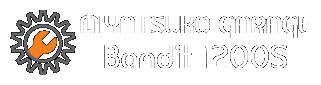
クラッチ操作を軽くする
スポンサードリンク
きっかけ
バンディット1200油冷ファイナルエディションのクラッチは、1,200ccという大排気量にしては軽いと思います。
が、しかし。
渋滞にはまったり、ロングツーリングだと辛くなってくるのも事実。
重いものは重い!!
ということで、左手の負荷軽減、さらにはコントロール性向上のため、
改善することにしました。
軽くする方法の検討
クラッチを軽くする方法としては、以下の3つが思いつきます。
1.マスターシリンダー交換
2.クラッチベアリングシステム導入
3.クラッチレリーズ交換
1つめはもっともオーソドックスで、改善が期待できます。
ラジアルのマスターにしてピストンの距離を稼ぐことにより、
握る量は増えますが小さな力で済みます。
自転車のギアををイメージすると分かりやすいかも。
ギアを軽くすると、なかなか進みませんがペダルは軽くなりますよね。
次に2つめのクラッチベアリングシステム。
これは、とねさんに教えていただいた優れものです。
レバーの軸をベアリングにしてしまうアイテム。
具体的にはコレのことです。
↓
RCエンジニア クラッチベアリングシステムスズキ
とても安いので、まずはこれを導入してみるのも良いかと思います。
で、最後の3つめ。
軽くする原理は1つめのマスターシリンダー交換と同じです。
レリーズのピストン径を小さくして、距離を長くする、というもの。
ただ、効果はマスターシリンダーの方が大きいみたいです。
06用はこれ。
〜05まではこれ。
ということで色々特徴がありますが、
みやつこは確実に効果が見込めるマスターシリンダー交換を選択しました。
マスターシリンダー選び
候補としては、ブレンボ、ニッシン、ゲイルスピード、といったところでしょうか。
みやつこが購入した当初はゲイルスピード製はなかったので、2択でした。
一番安いのがニッシンのラジポン。鋳物です。
セミラジアルというのもありますが、ラジアルが良いと思います。
みやつこは、ブレーキはこれを使っています。
次にゲイルスピード。
鍛造でレシオ可変(左)であることを考えるとリーズナブルだと思います。
レシオ可変じゃないやつ(右)は、もうちょっと安いですね。こちらでも十分かと。
最後が言わずと知れたブレンボ。
レシオ可変タイプと固定タイプがありますが、
可変タイプの方が、その構造からほんの少し機能的に劣る部分があるそうで、
固定タイプの方が玄人好みらしいです。
結論としては、Bandit1200のカスタムテーマ「豪華」に従い、ブレンボを選びました。
高いですが、やっぱり高級感あって格好良いじゃないですか(笑)
ちなみにBandit1200の場合は、ピストン径は19φくらい無いと
クラッチが切れにくいことがあるので、16φは選ばない方がいいです。
みやつこは最初16φを使ってましたが、結局19φに買い換えました。
用意したもの
・ブレンボクラッチマスターシリンダー 19φ × 18mm
・ブレンボマスタータンク
・タンクのホースを止める金具
・マスタータンクホース
・リザーバータンクステー(アントライオン)
これはお好みですね。ブレンボ用は色々出てますので。
・GOODRIDGE クラッチホース
・GOODRIDGE1.00のバンジョーボルト
純正クラッチリリース側もなぜか1.00だったような気が。間違ってたらすみません。
・GOODRIDGE バンジョーアダプター 2つ
こんな感じです。
マスターとホースを変えるだけでも、こうしてみるといろいろ必要ですね。
クラッチホースは純正が大体1340ミリなので、
1510ミリを購入しました。
純正だとマスターを変えると全く届かないので長めの物を購入。
実際は少し長かったです。もう少し短いのが良いと思います。
クラッチマスター交換
では、ラジポンを取り付けていきます。

まずはシートと左サイドカバーを外します。
サイドカバーは六角ネジ1本で止まってるだけ。

つぎに、純正ホースを取り外すために写真右のようにタンクをずらします。
タンクはシート下の2本のボルトを外せば外れる。
完全に外す必要はないので、
分厚い雑誌か何かを間に挟んでタンクをずらしてあげるといいと思います。

クラッチのリザーバータンクを開けてフルードを抜き取ります。

当初は1000キロちょっとしか走ってないのですが、かなり黒ずんでました。
かなりの高温に晒されているようです。

クラッチのブリーダーバルブに注射器を差し込んで、フルードを抜きます。
レバーをカチカチして握ったまま維持→バルブ緩める→注射器で吸う→バルブ締める
これの繰り返しでフルードを抜きます。

完全に抜くのは難しいので、ホースを外すときはフルードがこぼれてきてもいいように
下に受け皿を用意しておくといいかも。
もちろん水もです。
そしたらマスター側もバンジョーボルトを外してホースを取る。

純正のホースを外します。
小さな穴の所だけタイラップで止めてあるので切断。

外したのがこちら。
ただのまっすぐなホースじゃないんだね。

マスターシリンダーを取り外します。
ここで、忘れちゃいけないのがクラッチレバーに接続されたライン。
写真左の白っぽい奴です。これを引っこ抜きます。
これはクラッチを握らないとエンジンが掛からないようにしているもので、
抜いてしまうと当然エンジンがかからない。
ブレンボマスター用にこの配線を活かすスイッチが売ってますが、7000円くらいするみたいです。
ただのカプラーと線にこの値段はもったいないので、直結することにします。
2本の線の片側を雄端子にギボシ加工して互いに差し込めばオーケー。
これでクラッチ握らなくてもエンジンかかります。
(※安全装置の解除ですので、もちろん自己責任です。)

マスター一式を外します。

ブレンボマスター、ホルダーなど一式を取り付けます。
スイッチボックスにレバーが当たるので、目一杯左に寄せて付けた方がいいです。

次にホースを取り回して取り付けます。↑な感じに取り回しました。
エア抜き作業

最後にエア抜きをします。まずはマスター側から。
写真撮るのをわすれましたが、ブレンボマスターはマスター部分にもエア抜きバルブがあります。
レバーをカチカチしてるだけじゃ全く抜けませんでした。
エア抜き手順はさっきと一緒で
レバーをカチカチして握ったまま維持→バルブ緩める→注射器で吸う→バルブ締める
これでタンクにフルードが無くなってきたら足していきます。
ある程度やるとレバーを握っていないとタンクにフルードが逆流してくるようになります。
今更ですが、ブレンボマスターのエア抜きバルブには、
11mmのメガネかスパナが必要です。
奇数サイズは持ってないかもしれないので要注意。
バンジョーボルトも種類によっては13mmだったりします。

そしたら上の写真のようにクラッチレリーズ側でエア抜きをします。

以上で完了です。
レバーがスイッチボックスに当たる
スイッチボックスが大きいのか、
レバーがスイッチボックスに当たってしまい最後まで握れないようです。
最後まで握れなくとも19φならクラッチは切れるのですが、
あまり気分が良くないので対策をします。

そこで、このオフセットカラーという
マスターとハンドルの間に挟めてマスター自体を前に出す物を装着しました。
これで6ミリ前に出るので使いやすくなりました。
ボルトを少し長めのもの(25ミリくらい)に変える必要があります。
軽くなった?
で、肝心の効果ですが、
めちゃくちゃ軽い!!
ん? これで切れてるの?
ってまず最初に感じたのですが、それほど軽くなりました。
そしてラジポン効果によりピストンが動く距離が増えているので
半クラッチなど操作性も向上しているように思います。
値段はかなり張りますけど、
確実に軽くなります。
もしかしたらちょっと難しく感じるかもしれませんが、
エア抜きも慣れれば簡単ですし、特に難しいことはないです。
クラッチが重くて困っている、
もっと軽くしたいという欲求がある(笑)、
単純に格好いい!ということでブレンボにしたい、
そんな方にはぴったりな内容だと思います。
クラッチ操作性向上、疲労軽減に加え見た目向上による所有感も満たしてくれます。
ぜひ試してみてください。
きっと感動を味わえますよ。
スポンサードリンク






![【エントリーでポイント5倍】アクティブ(NISSIN) [82511911] クラッチマスターシリンダー [ラジアル/CASTING] φ3/4 (19mm) [ボディー:GLD/レバー:BLK]【送料無料】【エントリー期間:10/22 10:00?10/25 23:59】](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fedenki%2fcabinet%2factive02%2fed967871.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fedenki%2fcabinet%2factive02%2fed967871.jpg%3f_ex%3d80x80)
![【送料無料】[ゲイルスピード] VRCクラッチマスターシリンダー / VRC19-19CT / 汎用【02P25Oct12】](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fseed%2fcabinet%2f1107%2f110719310.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fseed%2fcabinet%2f1107%2f110719310.jpg%3f_ex%3d80x80)
![ゲイルスピード クラッチマスターシリンダー[RM]φ19/19mm/タンクステー RM19-19CT 【smtb-F】【送料無料】(一部除く)](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fpartsboxsj%2fcabinet%2f20100609-1%2frm19-19cts.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fpartsboxsj%2fcabinet%2f20100609-1%2frm19-19cts.jpg%3f_ex%3d80x80)
